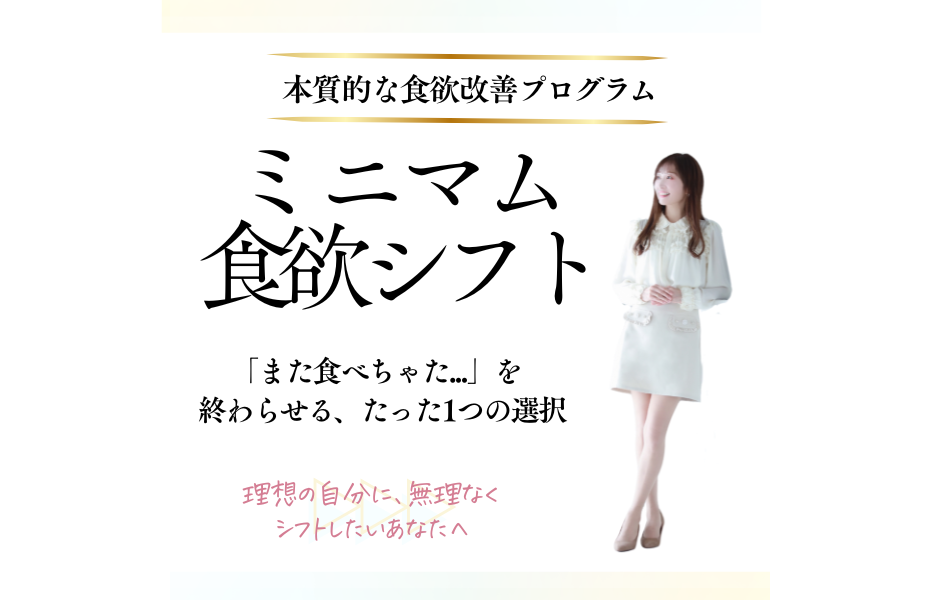カウンセリングでよく聞くこの言葉。
その後に続くのが、「そして、夜になるとお菓子が止まらなくなるんです」
夜の落ち着いた時間に、この感覚から抜け出せない方が多くいます。
この記事では、自分を出せないことがなぜ過食につながるのかを、
心と脳の仕組みからわかりやすく紐解きます。
「食欲がコントロールできない自分」ではなく、
「抑えてきた自分の声」を受け取るきっかけになれば幸いです。
目次
・ なぜ「自分を出せない」が過食につながるのか?
・ 「いい人」の仮面をかぶり続けるわたし
・ 食欲が教えてくれる“本音”のサイン
・ 抑圧された感情と、脳の仕組みの深い関係
・ 今日からできる「自分を取り戻す」ための小さなステップ
mokuji
目次
なぜ「自分を出せない」が過食につながるのか?
人間の脳は、本来「感じたこと」や「言いたかったこと」を表現するようにできています。
でも、
「こんなこと言ったら嫌われるかも」
「ここで空気を乱すわけにはいかない」
そんなふうに、自分の感情や欲求を何度も我慢していると、脳はどうにかその“ストレス”を解消しようとします。
そのとき、最も手っ取り早く快感を得られる方法のひとつが“食べること”なんです。
とくに、甘いものやジャンクフードは、脳内の報酬物質(ドーパミン)を強く刺激し、
一時的に「自分らしくない毎日」を忘れさせてくれます。
「いい人」の仮面をかぶり続けるわたし
40代以降のわたしたちには、
「家族のために頑張るのが当たり前」
「職場では輪を乱さないように」
「弱音を吐いたら迷惑」
といった、“自己抑圧型の優しさ”が染みついていることが多くあります。
それは素晴らしい美徳でもある一方で、「自分の本音や本当の願いを押し殺す習慣」でもあります。
そしてその結果として、夜ひとりになると、
「誰にも気を遣わずに、自由になりたい」
という本音が、食欲という形であふれ出すのです。
食欲が教えてくれる“本音”のサイン
過食や抑えられない食欲は、ただの"意思の弱さ"ではありません。
むしろ、あなたの中にある「聞いてほしかった声」や「ちゃんと感じたかったこと」が、
「食べること」を通じて訴えかけているサイン
であることが多いのです。
たとえばこんな気持ち、ありませんか?
自分だけ我慢していて報われない
感情を出したら壊れてしまいそう
本当は誰かに助けてほしい
これらはすべて、本来なら“言葉”で伝えられるべき大切な気持ちです。
でもそれが言えないなら、食べることでしか表現できなくなってしまう のですね。
抑圧された感情と、脳の仕組みの深い関係
脳科学の観点から見ても、感情の抑圧は強いストレスを引き起こし、
そのストレスが"快感ホルモン"を求めて暴走するという現象が起きます。
特に「孤独感」や「無力感」が強い時、
コルチゾール(ストレスホルモン)
ドーパミン(快楽ホルモン)
この2つがバランスを崩し、衝動的な食欲につながることがわかっています。
つまり、食べすぎの背景には、「自分の心を守るための仕組み」があるということ。
それを責めてしまうのではなく、やさしく解いてあげる必要があるのです。
今日からできる「自分を取り戻す」ための小さなステップ
過食や抑えられない食欲をやめる第一歩は、「食べること」を変えることではありません。
「本当の自分の気持ちを、1日1回でも感じてあげること」です。
たとえば、
朝、鏡を見ながら「今日の気分はどう?」と聞いてみる
夜、お風呂で「今日、言えなかったことは?」と自分に聞いてあげる
ノートに3行だけ「本当はこうしたかったこと」を書いてみる
たったそれだけでも、心は確実に反応します。
抑えてきた声が少しずつ出せるようになると、食欲という“代弁者”はもう必要なくなっていく、そんな方向に向かい始めます。